 |

|
|
|||
|
このブログでは、カテゴリー分けに出来ないため、
テーマを色別で表示しています。 |
ブログで使用した写真リスト
■ALL PHOTO LIST
レアモノ中西コレクションを公開
■思い入れコレクション集 |
 ■PAOSノベルティ |
 ■PAOSそば猪口 |
|||||||
|
■■チョコレート、無念の思い出
■■■勝見勝先生 ■■■影さんを悼む ■■2019年の新年所感 ■■■9年振りの台湾訪問と講演・展示会 ■■飯粒を残すような奴は出世しない! ■■「写真撮影」への思い入れ ■■「コーポレート・アイデンティティ戦略」改訂版を刊行予定 ■我がオフィス(事務所)転々記 ■■■STRAMD、9年目を前に終了、さて次なる展開は? ■■桑沢デザイン研究所以来の友人、坂本和正君逝く ■■■STRAMD第8期生修了、そして第9期生募集へ ■■9年目を迎えるSTRAMD(戦略経営デザイン) ■■王超鷹と中国の切り絵文化展、そしてPAOS上海のこと ■■盟友「木谷精吾」逝く ■イヌ型ロボット、AIBOから復活aiboへ ■■2018新年ご挨拶 ■■■「PAOSの次を創る」人材が欲しい ■ポルトガルの旅 ■■■「中西元男の世界」展を終えて ■■■「中西元男の世界」展 開催にあたって 2
■2019年02月
■2019年01月 ■2018年12月 ■2018年08月 ■2018年06月 ■2018年05月 ■2018年04月 ■2018年03月 ■2018年02月 ■2018年01月 ■2017年12月 ■2017年10月 ■2017年09月 ■2017年08月 ■2017年03月 ■2017年02月 ■2016年09月 ■2016年05月 ■2016年02月 ■2016年01月 ■2015年12月 ■2015年09月 ■2015年06月 ■2015年05月 ■2015年04月 ■2015年03月 ■2015年01月 ■2014年12月 ■2014年11月 ■2014年10月 ■2014年09月 ■2014年08月 ■2014年06月 ■2014年04月 ■2014年03月 ■2014年02月 ■2014年01月 ■2013年10月 ■2013年09月 ■2013年08月 ■2013年04月 ■2013年03月 ■2013年02月 ■2013年01月 ■2012年08月 ■2012年05月 ■2012年03月 ■2012年02月 ■2012年01月 ■2011年12月 ■2011年11月 ■2011年10月 ■2011年09月 ■2011年08月 ■2011年06月 ■2011年05月 ■2011年04月 ■2011年03月 ■2011年02月 ■2011年01月 ■2010年11月 ■2010年08月 ■2010年07月 ■2010年06月 ■2010年05月 ■2010年04月 ■2010年03月 ■2010年02月 ■2010年01月 ■2009年11月 ■2009年10月 ■2009年09月 ■2009年08月 ■2009年07月 ■2009年06月 ■2009年05月 ■2009年04月 ■2009年03月 ■2009年01月 ■2008年12月 ■2008年11月 ■2008年09月 ■2008年08月 ■2008年07月 ■2008年06月 ■2008年05月 ■2008年04月 ■2008年03月 ■2008年02月 ■2008年01月 ■2007年10月 ■2007年09月 ■2007年08月 ■2007年07月 ■2007年06月 ■2007年05月 ■2007年04月 ■2007年03月 ■2007年02月 ■2007年01月 ■2006年12月 ■2006年11月 ■2006年10月 ■2006年09月 ■2006年08月 ■2006年06月 ■2006年05月 ■2006年04月 ■2006年03月 ■2006年02月 ■2006年01月 ■2005年12月 ■2005年11月 ■2005年10月 ■2005年09月 ■2005年05月 ■2005年01月 ■2004年12月 ■2004年11月 ■2004年10月 ■2004年09月
好漢、長峰秀鷹逝く
・ 松尾紘出子 (2006/03/20) 思い出ベンチ ・ 花子 (2005/11/19) 小泉解散に思う。vol.3(8月18日) ・ Narumi Fukuda (2005/11/10) |
« 新年ご挨拶状と次世代デザインに向けて
|
メイン
|
どなたでもお聴きになれる講義です ■■■2009年に向けての新年挨拶状(PAOS設立40周年記念)2009 / 1 / 8前回の拙文を受け、2009年の新年ご挨拶状も、以下にアップさせて頂きます。どうぞ、ご高覧ご笑覧下さい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2009年が素晴らしい年でありますように 実験会社PAOS40周年 PAOS設立から遂に40年を迎えました。早稲田大学デザイン研究会の延長で、特段の事業的成算もなく始めた仕事が、よくぞこれまで続いたと思います。「企業経営の中に、見えるデザイン・見えないデザインを含めた成果を創出していこう」が当初目標で、創業時より自ら「実験会社」やがて「THINK CREATIVE」を標榜し続けてきました。その姿勢は今も変わりません。振り返れば成功も失敗も山積の星霜40年ではありましたが、可能な限り挑戦は続く、そして、一個人の寿命を越えていく「理念や使命の構築・実証」は既に出来ていると考えます。 先般、中国で「先生の美的経営は継承発展させます」と言われ驚きましたが、私自身も、高齢者なるも老齢者に非ず、が貫き通せればと願っております。これまでの長きにわたる多くの皆さまよりの信義とご芳情こそまさに宝物であり、多謝深謝です。 [昨夏に相次いで私(中西)の父母が鬼籍に入りましたので、個人としては本来服喪中ではあるのですが、PAOSなる組織そして運動体の長の立場として、敢えて新しい年に向け一筆取らせて頂く次第です。] 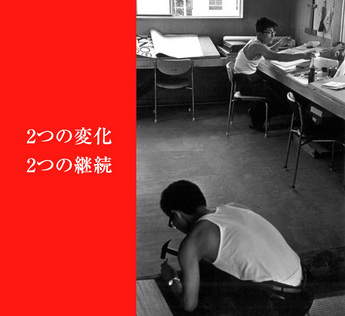 1. オフィス移転 このたび、表参道から六本木へ事務所を移転いたしました。上の写真は仕事場を自ら大工仕事で造りながら、…といった創業当時(1966年 高円寺)のものです。まさに隔世の感ありです。8年半過ごした表参道オフィスは駅直近で実に便利でした。ですが最近は、移転当初には一軒も無かった世界的著名ブランドショップのまさに真っ只中という立地になってしまい、騒音も多くまるで観光地と化した毎日を「これではPAOSらしくないな」と思っていましたので、よいタイミングの引っ越しだったと考えております。新オフィスは国立新美術館の正門真向かいです。東京ミッドタウンも六本木ヒルズも歩いて数分の、いわゆる最近話題の都心美術館ゴールデン・トライアングルの中に位置します。立地に相応しく美意識の高いビジネスが続けられればと願っております。 2. よりデザインコンサルティングへ 最近、「CIを導入してみたのだが効果が現れないので、相談に乗って貰えまいか?」と、遠方から経営者の方がお問い合わせに見えました。CIがブームとしてもてはやされた1980年代後半、導入を図った一部上場企業の約7割が「開発を依頼したが効果が無かった」と答えたという調査データが手許に残っていますから、CIなるものが如何に金儲けの具として使われていたか、いかに責任を果たすプロが少なかったかの、これは証左でしょう。近年流行のブランド戦略プロジェクトも、似たような結果を招くのではないのでしょうか。 「経営にデザインを幅広く活かす」分野で40年もの長いキャリアを重ねてきましたPAOSにとって、永年の経験と豊富な専門知識や美意識を活かした戦略デザインのコンサルティングは、今後の経営に最も必要とされるに至る分野と考えております。それゆえ現在社外の経験豊富なMBAを持つプロたちを含め、独自のコンサルタントチームを編成しようと計画推考中です。元々、「デザインという切り札を持つ経営コンサルタント」を目指し成果を生み出してきたPAOSですが、経営に美意識を幅広く採り入れていく営為は、右脳と左脳、感性と知性を融和して活かすという意味において、今後ますます重視されるべきデザイン分野と見ております。しかし、見渡すに最近はレベルの低いアイデンティティ・デザインや精度感に欠ける造形表現が多過ぎます。その結果がこの国の美的インフラ水準を低下させ、長期的なマーケティングツールとして機能し得ないロゴを氾濫させています。 「シンボルは宝石の如く扱え」「特別なアイテム展開を除いてパターン使用は避けよ」「ひとつのロゴに二つの視覚ポイントは設けるな」「時間を超越したマネジメントツール(道具)を創れ」「美的長期的社会資産を生み出せ」…これらの基本姿勢はあまりにも当たり前のロゴデザイン原則の一端ですが、最近はそれすらも考慮されていない美的品質の低いパソコンまかせのインスタントデザイン事例が目に余ります。CIやブランド戦略が一般化してきた今は、クライアント側に立って20年30年先を考えアドバイスできる「知の人・目の人としてのコンサルタント」が、もっと増える必要があるのではないでしょうか。コーポレートレベルのデザイン水準が近視眼的意思決定の所産であってはならないことは、既に歴史上の名作とも呼べる著名デザイン事例が証明してくれているところです。 W.グロピウスは、「デザインとはあらゆる分野の共通公分母」と述べましたが、確かに全ての人工物は少しでも美しい方が良い、快適であるべきだという意味での、公分母性や分野横断的価値軸をデザインは内在させているのだと言えるでしょう。しかし、これは工業化時代におけるデザインのミッション(使命)であって、情報化時代・成熟社会ではもう一段高い位置づけを占めるべきだと考えています。「技術・経済・文化・社会の関係性に秩序と調和と個性をもたらし、人に生きる歓びを創出していく境界融合機能」こそがデザインの新たなるミッションとなるべきでしょう。「文化成長が経済成長を牽引する構造」への変換、これは長くPAOSが志向し主張し続けてきた指針ですが、いよいよその時代の兆しが見え始めたと感じております。 3. 継続の継続 判じ物のようなタイトルで申し訳ありません。「実験会社」という姿勢に加え、「記録のPAOS」を標榜し実践を重ねて来たのが私たちの歩みでした。専門とする分野における黎明期の世界的な研究資料の保存、お引き受けしたプロジェクトの開発記録やトップマネジメントの発言集等は、その企業自体にも今や殆ど残されていないでしょう。「賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ」と言いますが、例えば企業のCIプロジェクト(真の理念構築や長期経営指針の確立とその効率的具現化)をお引き受けした際の重要な作業の一つは、社史の読み込みです。山のように発行されるわりには最も読まれない本の代表とも言われますが、その内容の客観的分析にこそ企業固有のDNAの発進源や体質・社風成立の根や芽の発見があります。加えて、仮に歴史的累積に逆らう提案をしたとしても、結果は受け容れられないか短期消滅に終わるかのどちらかで、その後何十年単位の存立資産や経営資源にはなってくれないものです。勿論、デシジョンメーカー(意志決定者)としての優れたトップマネジメントの存在無くして成果は期待出来ないのですが、連続体として企業の来歴を精査していく延長線上にこそ、将来の可能性は隠れている、というのがこれまでの実感です。ルールを定めてアーカイビング(記録集積)していくことの重要性はここにあります。たとえばPAOSで続けております「西新宿定点撮影記録」は2009年7月で丸40年を迎えますが、最近になって取材やTV放映等の活用依頼頻度がどんどん増えてきております。また、21世紀を期して始めましたワールド・グッドデザイン社の、世界を代表するデザイン賞受賞作品情報集積「WGDアーカイブス」事業も、これまで紆余曲折あり苦労の連続でしたが、新しい体制と優秀な協力者のもと、ようやく軌道に乗り、5年分全10巻の発刊に及びました。先進各国が国家戦略として情報アーカイビングを実践している中にあって、「情報貧国:日本」が最近ようやく話題に上るようになってきましたが、その要因は、アーカイビング意識の低さにあると言われます。確かに、先端の話題や流行ばかり追いかけて、長期展望に基づく文化的価値・社会資産の創造や戦略的な個性創出力や発想などが不足している国民性、そして調整行為と創造行為の重要性の区別がつかない企業の近視眼的価値認識力、これらの原因の多くはアーカイビングに対する認識の甘さや戦略的仮説構築力のつたなさにあると思えます。 4. 人材育成、知財残し人残しへ 「金を残すは下、仕事を残すは中、人を残すは上」とは、後藤新平の死の直前の言葉です。思い返せば、師もなく金もなくコネもないところから始めたPAOSのビジネス40年は、実に多くの、他の人には体験できない稀有なる経験と実績を残してくれました。本当はそのプロセスこそが最も重要なのですが、これまでに生み出された数々のノウハウや資料・情報の蓄積も馬鹿になりません。それらを活かしていく最善の策こそ、次世代に「拡デザイン」理念やソフトの価値を伝え、新しい人材を育てていくことでしょう。そのためPAOSでは、永年にわたり極力デザイン系というよりは経営系の学生主体に教育活動を展開してきました。40年余にわたる膨大な仕事上の重要記録は大切に保存してあり、特に主要と思える5つのプロジェクトについてはメモ用紙の一枚、経営者の呟きまで保管されております。1960年代の萠芽期から始まったPAOSの主要な活動プロジェクトは、振り返ってみても、歴史的に今後当分は起こりえないであろうと想像される、世界史上で日本という国が最も燦然と輝いた時期の証しであり、産業史的に貴重なアーカイビングと言えます。 新事業起こし セキスイハイムのビジネス確立戦略、ダイエー中内功社長の生音声、ミスター百貨店 山中慣松屋社長との10年余に及ぶ蘇業成長策のやり取り、福武書店からベネッセコーポレーション、伊奈製陶からINAX、等の経営大変革期トップの志向記録、電電公社からNTTへの民営化時の真藤恒総裁および社長の意志決定記録、伊藤忠商事の丹羽宇一郎現会長がNew CI事務局長を務めた世界的理念開発プロジェクト物語等々、それらに代表される貴重資料を、次代の人材育成や研究素材としてどこかで有効活用することが可能であればと願っています。多ければいいというものではないのでしょうが、たとえば諸記録に関わる写真資料だけでも約20万カットを越える量は在ろうかと推測します。 これらのPAOS記録に関しては、かつて中国から、「天安門広場にある歴史博物館内にかなりの収納展示スペースを設け、日本語に堪能な学者20人をつけて系統的に資料整理を行うから、一度預けてくれないか?」との申し出を受けました。さすが大河のような文化の潮流を持つ国は考えることが違うな、と感心しましたが、守秘義務上の問題を鑑みお断りした経緯を持つ貴重資料集積です。差し迫った問題は、これら記録のほとんどが未だアナログ状態でしか保存されていないという実態ですが、さてどうするべきでしょう? このたび改めて、バブル経済最盛期1988年制作のPAOS設立20周年記念時の映像資料を引っ張り出して見てみましたら、《美的経営》とタイトルが付けられ、「日本型経営はやがて崩壊する」「これからの日本は狩耕型マネジメントへの移行と確立が必要」「次には文化と環境と人間の時代がやってくる」等々、予測や提案が並んでいました。狩耕型経営とは、知的美的創造力に秀でた1人の狩人が発想提案し、それを多くの農耕型組織人が受け皿となって発展させていくという、わが国独自の新しい経営モデルです。いよいよ対症療法より根源療法を必要とする時代に及んだ昨今のわが国ですが、この20年前の仮説提案に極めて近い変革時期が到来しているのではないかと考えながら、懐かしく旧作に見入りました。 仮説の構築力はわれわれのビジネスにとって実に重要ですが、「THINK CREATIVE」をPAOSのスローガンに定めた頃、スタッフ用の机上には「今考えていることはもう旧い」と併記されていました。最近、上海の復旦大学での講演時に揮毫を求められ「創造脈動」と書きましたが、振り返ればPAOSは実に多くの表現や用語、ノウハウ、チャート、パラダイム等を創り、新しいビジネスフィールドや著作権の創出にチャレンジしてきました。こうした姿勢を失い整理調整や妥協を仕事と考える時が来たら、それはPAOSが存立理由を失う時でしょう。絶えざる創造の歓びと苦しみこそが私たちの象徴行為と考えております。いつまでも青さの抜けないPAOSを、2009年も何卒よろしくお願い申し上げます。
PAOS & ワールド・グッドデザイン 代表
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
冒頭の図版はこれまでのPAOS40年の活動の一端を掲出してみたものです。 1968〜2008 40年の歩みとプロジェクト成果 PAOSの歩みが具体的に始まったのは、1962年提案発表の「早稲田大学デザイン学部設置への試案」からと言えるでしょう。いわばPAOS前史にあたりますが、この時、将来のデザイン発展のためには作家作品主義とは別の、分野を越えた「組織で創造するデザイン」、経営基盤や社会インフラとなる「システムとしてのデザイン」を志向する、「デザインの分野創造拡大」に向かって歩み始めることとなりました。結果、現在PAOSでは次の6軸でデザインを捉えるのが慣例です。 6つの核・拡デザイン 1.政策・方針のデザイン 2.表現・表象のデザイン 3.新事業・事業領域のデザイン 4.理念・企業存立のデザイン 5.公共的・社会的価値のデザイン 6.文化的・環境的価値のデザイン PAOS40年余のワークスタイルにおける最大の特色は、企業の存立理念や経営方針の構築デザインから始めるところにあると言ってよいかと思います。そうした姿勢で40年余、多くのクライアントそしてプロジェクトに恵まれ、また自らの著作や研究成果の発表も行ってまいりました。それらが、裏面にご覧いただけます各種「見えないデザイン・見えるデザイン」、つまり数々のコンセプトから表現、デザインシステム展開等です。ランダムな一部の事例抜粋ですが、ご高覧願えれば幸甚です。 PAOS(Progressive Artists Open System)は、常々オープンシステムを標榜し、多くの外部クリエイターの方々のご協力を仰いでまいりました。ここでは、特に主要エレメントデザインに関わって頂きました皆さま方のお名前を、感謝の気持ちと共に列記させていただきます。 Co-creator(敬称略・五十音順) 秋田 寛 五十嵐 威暢 礒部 司 梅田 正徳 梅原 豊和 亀倉 雄策 倉地 孝幸 小泉 均 左合 ひとみ 佐藤 卓 しりあがり 寿 新村 則人 仲條 正義 平松 暁 藤兼 雅幸 松永 真 三木 健 村上 輝義 レイ 吉村 Chermayeff & Geismar Associates Colin Forbes, Pentagram Helmut Schmid Henry Steiner Herb Lubalin ※本Blogへのご意見・ご感想をお待ちしております。 こちらまでメールをお寄せください。 Blog内にてご紹介させていただく場合もございますので、何卒ご了承願います。 投稿者 Nakanishi : 2009年01月08日 12:00 |
| ©2004 PAOS, All Rights Reserved. 著作権に関して |



