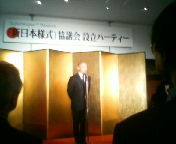|

|
|
|||
|
このブログでは、カテゴリー分けに出来ないため、
テーマを色別で表示しています。 |
ブログで使用した写真リスト
■ALL PHOTO LIST
レアモノ中西コレクションを公開
■思い入れコレクション集 |
 ■PAOSノベルティ |
 ■PAOSそば猪口 |
|||||||
|
■■チョコレート、無念の思い出
■■■勝見勝先生 ■■■影さんを悼む ■■2019年の新年所感 ■■■9年振りの台湾訪問と講演・展示会 ■■飯粒を残すような奴は出世しない! ■■「写真撮影」への思い入れ ■■「コーポレート・アイデンティティ戦略」改訂版を刊行予定 ■我がオフィス(事務所)転々記 ■■■STRAMD、9年目を前に終了、さて次なる展開は? ■■桑沢デザイン研究所以来の友人、坂本和正君逝く ■■■STRAMD第8期生修了、そして第9期生募集へ ■■9年目を迎えるSTRAMD(戦略経営デザイン) ■■王超鷹と中国の切り絵文化展、そしてPAOS上海のこと ■■盟友「木谷精吾」逝く ■イヌ型ロボット、AIBOから復活aiboへ ■■2018新年ご挨拶 ■■■「PAOSの次を創る」人材が欲しい ■ポルトガルの旅 ■■■「中西元男の世界」展を終えて ■■■「中西元男の世界」展 開催にあたって 2
■2019年02月
■2019年01月 ■2018年12月 ■2018年08月 ■2018年06月 ■2018年05月 ■2018年04月 ■2018年03月 ■2018年02月 ■2018年01月 ■2017年12月 ■2017年10月 ■2017年09月 ■2017年08月 ■2017年03月 ■2017年02月 ■2016年09月 ■2016年05月 ■2016年02月 ■2016年01月 ■2015年12月 ■2015年09月 ■2015年06月 ■2015年05月 ■2015年04月 ■2015年03月 ■2015年01月 ■2014年12月 ■2014年11月 ■2014年10月 ■2014年09月 ■2014年08月 ■2014年06月 ■2014年04月 ■2014年03月 ■2014年02月 ■2014年01月 ■2013年10月 ■2013年09月 ■2013年08月 ■2013年04月 ■2013年03月 ■2013年02月 ■2013年01月 ■2012年08月 ■2012年05月 ■2012年03月 ■2012年02月 ■2012年01月 ■2011年12月 ■2011年11月 ■2011年10月 ■2011年09月 ■2011年08月 ■2011年06月 ■2011年05月 ■2011年04月 ■2011年03月 ■2011年02月 ■2011年01月 ■2010年11月 ■2010年08月 ■2010年07月 ■2010年06月 ■2010年05月 ■2010年04月 ■2010年03月 ■2010年02月 ■2010年01月 ■2009年11月 ■2009年10月 ■2009年09月 ■2009年08月 ■2009年07月 ■2009年06月 ■2009年05月 ■2009年04月 ■2009年03月 ■2009年01月 ■2008年12月 ■2008年11月 ■2008年09月 ■2008年08月 ■2008年07月 ■2008年06月 ■2008年05月 ■2008年04月 ■2008年03月 ■2008年02月 ■2008年01月 ■2007年10月 ■2007年09月 ■2007年08月 ■2007年07月 ■2007年06月 ■2007年05月 ■2007年04月 ■2007年03月 ■2007年02月 ■2007年01月 ■2006年12月 ■2006年11月 ■2006年10月 ■2006年09月 ■2006年08月 ■2006年06月 ■2006年05月 ■2006年04月 ■2006年03月 ■2006年02月 ■2006年01月 ■2005年12月 ■2005年11月 ■2005年10月 ■2005年09月 ■2005年05月 ■2005年01月 ■2004年12月 ■2004年11月 ■2004年10月 ■2004年09月
好漢、長峰秀鷹逝く
・ 松尾紘出子 (2006/03/20) 思い出ベンチ ・ 花子 (2005/11/19) 小泉解散に思う。vol.3(8月18日) ・ Narumi Fukuda (2005/11/10) |
« 目標をもっと高く置くべきないか? 「高度デザイン人材育成事業」 | メイン | 青色発光ダイオードの発明者:中村修二先生のお話から。 » ■■新日本様式(Japanesque Modern2006 / 2 /21「新日本様式」と名づけられた国家プロジェクトの発足イベントが新橋演舞場にて催された。外務省・経済産業省・国土交通省・文化庁と4中央省庁相乗りと大変力の入ったプロジェクトであり、式典のトリは坂田籐十郎、パーティの挨拶は市川海老蔵を迎えての豪華版であった。
このように、現代で「新」日本様式と言う場合、次の4軸で捉えられると私は考えこれまでも実践してきた。
投稿者 Nakanishi : 2006年02月21日 18:15 |
| ©2004 PAOS, All Rights Reserved. 著作権に関して |